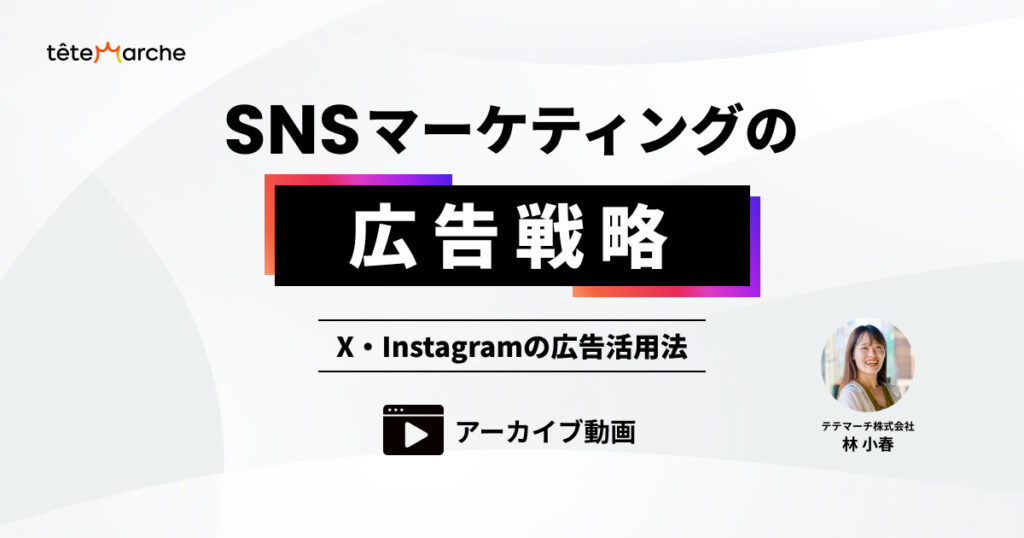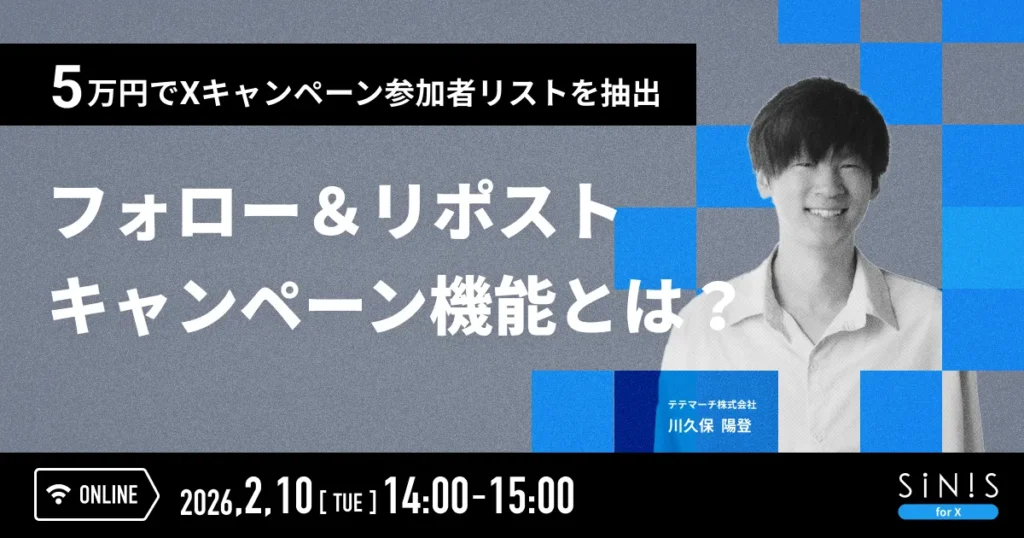没入は“仕掛ける”のではなく“生まれる”もの。スペースマーケットが考える没入体験の方程式
Date : 2025/06/11
全国のあらゆるスペースを時間単位で貸し借りできるプラットフォーム「スペースマーケット」を運営する株式会社スペースマーケット。同社とテテマーチが、ブランドとファンのより深い関係構築と、SNS上での熱量の高いUGC(ユーザー生成コンテンツ)創出を最大化する新たなプロモーション手法「ブランド没入型体験プロモーション」の提供を開始しました。
テテマーチとスペースマーケットが業務提携「ブランド没入型体験プロモーション」を提供開始
今回は、スペースマーケット社の久野祐揮さんに、サービスローンチに至るまでの経緯、サービスに込めた想い、そして実現したい世界観について伺いました。また、スペースマーケットの空間が生み出す独特の没入体験について、さまざまな事例や考え方をもとに語っていただきました。
目次
「空間のメディア化」構想から生まれた「ブランド没入型体験プロモーション」
三島:
今回の業務提携は、弊社からのご提案がきっかけでした。私たちの「ブランド没入型体験プロモーション」というアイデアに対して、スペースマーケットさんは当初どのような印象をお持ちになりましたか。また、そこから最終的に「一緒に取り組もう」と、ご決断いただいた経緯についてお聞かせください。
マーケティングの観点からすると、そのイベントが開催されるスペースは非常に「メディア価値のある場所」と言えます。この空間のメディア価値を活かして、何らかの形で空間のさらなる利活用につなげられないものかと、2025年に入ってから考えていたのです。
久野:
まず前提として、スペースマーケットは「スペースを貸したい人」と「スペースを借りたい人」をマッチングするプラットフォームです。そして、スペースを借りたい人は、例えば「パーティーをしよう」などと、何らかのイベントを楽しもうという意欲が高い状態にあります。
しかし、それを当社だけで企画から実行まで行うのは現実的に難しいので、パートナーを見つけて一緒に取り組むのが良いと思っていました。まさにそんなタイミングで、今回のお話をいただいた次第です。

三島:
久野さんたちの思惑と私たちの提案が、絶妙なタイミングで合致したのですね。「ブランド没入型体験プロモーション」のように特定のスペースをジャックした取り組みには、私たちも大きな価値を感じています。
弊社では、ポップアップイベントの支援も多く手がけていますが、「何ヶ月もかけて準備したのに、たった3日で終わってしまうのは惜しい」といった声が結構ありまして…。より長期的な取り組みができる方法を模索した先に、スペースマーケットさんとの協業というアイデアが浮かんだのです。
ちなみに、今回の取り組み以外に、空間をメディアとして活用するようなアイデアはありましたか。
久野:
「空間のメディア活用」とは少し異なりますが、利用してくれたゲストに対するフォローアップなどは考えています。例えば、飲料を販売する企業と連携して、スペースマーケットの利用者様へ数日前にメールで情報をお届けして利用を促すようなものです。
これにより、利用者様は手軽にイベントの準備ができ、私たちにとっては購入意欲の高いお客様にアプローチできるため、双方にとってメリットのある施策として期待しています。
三島:
ある意味、最強のレコメンド施策ですね。
久野:
コロナ禍以前には、大型イベントを実施する事業なども実施していましたが、よりプラットフォームとしての価値を発揮できるビジネスモデルを模索する中で、“空間”そのものが持つメディアの価値を最大限に引き出すという考えに至ったのです。
“利用者主体”が生み出すスペースマーケットの没入体験
三島:
先ほどコロナ禍の話が出たので気になったのですが、スペースマーケットの利用シーンや利用者層は、コロナ禍の前後でどう変化しましたか。
久野:
コロナ禍で大人数のパーティー利用は減りましたが、オンライン会議が増えたことで、少人数のビジネス利用は逆に増え、それが今でも定着しています。実は、利用数で見ると最も多いカテゴリーはビジネスなんですよ。ソロワークで使われるワークボックスのような個室は、1日に4回転することもあります。
最近ではパーティー利用が復活しているほか、例えば、ダンススタジオとしての利用、推し活、ボードゲーム、映画鑑賞など、あらゆる利用用途が伸びています。このように、利用者様が積極的におもしろい使い方を発明してくれているような状況です。
冒頭の話に戻りますが、ユーザーは何かしら目的を持ってスペースを借りています。つまり、箱(スペース)ありきではなく「コト消費」がベースになっているのです。
例えば、「ゲームマーケット」という国内最大規模のボードゲームイベントで新しいゲームを手に入れ、それを友達同士で遊ぶことになったとします。その際、「どうせなら、いつもとは違う素敵な空間で遊びたい」と考えるかもしれませんよね。そうしたストーリーから選ばれた空間で行われる「ボードゲームお披露目会」は、きっと没入感のある体験になるはずです。

三島:
確かに。ちなみに、「没入」という言葉は最近のトレンドワードでもありますが、スペースマーケットさんはこの言葉をどのように定義していますか。
久野:
私たちが考えている「没入」の定義は、「何かに熱中している状態」に近いと思います。
例えば、チームラボさんが生み出しているクリエイティブは“作り手主体”の没入体験です。それに対して、当社は「スペースを利用する人が主体の没入体験」だと捉えています。私たちは、利用者が前のめりになっている状態に、「こうするともっと楽しめますよ」と補助線を引いてあげるイメージです。
三島:
利用者自身がスペースの使い方を発明しているという話にもつながりますね。この現象はスペースマーケットさんが意図的に作り出しているのでしょうか。
久野:
いえ、どちらかというと自然発生的に生まれたものです。データを見ていると、この現象を引き起こす「イノベーター」と呼べる人々が世の中にいることが分かります。そのイノベーターたちが、自由にカスタマイズしてスペースを利用することで、新しいユースケースを次々と生み出しているのです。
最近だと、東京駅などの主要バスターミナル駅の近くで早朝から数時間ほどスペースが利用されていることを見つけました。詳しく調べてみたところ、遠方から夜行バスで推しのライブに東京まで来られた方が、到着後、開演までの待ち時間を過ごしたり、ヘアメイクなどの準備のために利用されたようでした。
三島:
それは面白いですね!
久野:
他にも、パーソナルジムのトレーナーが半年間で数百回もスペースを時間借りすることで、不動産を持たずにお客様の都合のよい場所に合わせた利用をするケースもあります。これらは私たちが提案して生まれたものではなく、ゲストの利用から発見しています。
マジョリティではないけれど、理に適った使い方をしている事例をピックアップして提示することで、共感する利用者様が増えていく。このように、かっこよく言えば「データドリブン」なアプローチで、すでにあるケースをフックアップしています。
三島:
利用者同士でイノベーションが生まれているんですね。お客様の能動的なアクションの中で、「自然と没入体験が生まれている」と表現する理由もよく分かりました。
ポップアップでも店舗でもない「第3の没入体験」
三島:
久野さんは、従来のプロモーション手法と「ブランド没入型体験プロモーション」を比較して、どのような独自価値を提供できると考えますか。
比較対象として私が思い浮かべるのは、冒頭でも触れたポップアップストアです。ポップアップストアは準備に数ヶ月かけても、開催期間はだいたい3日から長くても1週間程度と、あっという間に終わってしまいますよね。
瞬間的な話題性や集客力は魅力ですが、もっと持続的なエンゲージメントにつなげられないだろうかと考えたときに、その課題を解決できるのが「ブランド没入型体験プロモーション」だと考えています。

久野:
ポップアップストアに加え、「旗艦店」も比較対象としたとき、これら3つは提供できる体験の「濃さ」と「期間」に違いがあると思います。
まず、ポップアップストアは濃密な体験と高い話題性を生み出しますが、開催期間に対するコストが大きく、実施後すべて取り壊さなければならないので、「資産として残らない」というデメリットを抱えています。
一方、旗艦店はポップアップストアほど濃い体験を目指すわけではないですが、長期的な顧客接点を築けることを前提としています。それゆえ、スタッフの手配や施設のメンテナンス、集客などの業務が常に発生し、どうしても「手離れの悪い」状態になりがちです。
今回の新サービスは、この両者のメリットを掛け合わせた、まさに「いいとこ取り」をしたものだと考えています。ポップアップストアのような濃い体験を提供しつつ、運営はスペースマーケット側が担うため、旗艦店を運営するような「手離れの悪さ」がありません。これにより、質の高いブランド体験を比較的長期間にわたって運営することが可能になります。これが、スペースマーケットならではの独自価値だと考えています。
三島:
スペースマーケットの大きな特徴は、お客様が目的を持って利用する点にあると久野さんがおっしゃっていた通り、なんとなく訪れる場所ではないからこそ、提供される体験に対して能動的になりやすいんですよね。
さらに重要なのは、ユーザーが「アレンジを加えられる余地」があることだと感じています。映画鑑賞やスポーツ観戦、好きなアイドルのライブ映像の鑑賞を、特別な人と特別な空間で楽しめる。このアレンジ性が、没入感をさらに深めるのではないでしょうか。
久野:
そうだと思います。マスではないけれど、世の中には「自分なりに楽しみたい」というアレンジ欲求を持つ人々が存在します。そういう人たちが、スペースマーケットというプラットフォームをうまく活用してくれている。そして私たちは、その動きをデータで見ることができるという強みを持っています。
三島:
利用者が自ら新しいスペースの使い方を開発し、それがまた新たな需要を生む。その循環にブランド体験を組み込むことができれば、これまでにないエンゲージメントが生まれるかもしれませんよね。
久野:
スペースマーケットの空間で体験される「コト」が楽しいものであればあるほど、そこに自然に溶け込んだブランドや商品は良い印象として残りやすいはずです。限定的なプライベート空間だからこそ、よりパーソナルな体験として記憶に刻まれる可能性があると考えています。
企業が「没入体験」を生み出す条件
三島:
没入体験は価値あるものですが、企業側が「没入体験ができます!」と過度に訴求することで、ユーザーが没入を楽しむ“余白”を奪ってしまいかねません。「没入」というキーワードを扱う上で、意識すべきことは何だと思いますか。
久野:
そのブランドのキャラクター性や「パーソナリティ」を見失わないことが大切だと思います。
例えば、私が大好きな地方のクラフトビールメーカーさんは、味や香りだけではなく、独自の世界観やデザイン、ネーミングなどの「情緒的価値」を押し出すことで、それを愛するファンを多く獲得しています。だからこそ、もしそのメーカーが超プレミアムなビアガーデンをやったとしたら、何となく「らしくないな…」と感じてしまう気がします(笑)。
「世の中で流行っているから」という理由でブランドに何かを外付けすると、途端に違和感が生じてしまう。ブランドのコアにあるものをもっと深く体験できる方向を模索しないと、良い体験は生まれません。「何を取って何を取らないか」が明確で、身の丈に合ったことをしているブランドが、強いブランドなのだと思います。
三島:
まさにそうですね。没入体験に限らず、SNS運用でも同じことが言えます。企業のブランドイメージとは異なる投稿を目にすると、乗るべきトレンドとそうでないトレンドの見極めがいかに重要かを痛感します。
とはいえ、ポップアップにしても体験型イベントにしても、アイデアが飽和してきている感覚があります。あらゆるものがコモディティ化しつつある中で、記憶に残り、熱狂を生むような体験を企画するには、何が大切だと思いますか。
久野:
そのブランドやプロダクト自体の「オタクになる」ことじゃないでしょうか。
圧倒的な熱量でコンテンツやブランドに触れることで、本質的な面白さを自分ごと化して理解できる。その上で、プランナーとしての客観的な視点をバランス良く組み合わせると、熱狂できる企画を生み出せるのだと思います。
また、外部の人間としてすごく重要なのは、クライアントが当たり前すぎて見過ごしているブランド価値の良さを、「それは良いものです」とシンプルに伝えてあげることですね。当事者ほど、その価値に気づいていないことが多いですから。

三島:
「今ある価値では他社との差別化が難しいので、新しい価値を作りたい」という思考に陥っているパターンですね。支援する側として、非常に共感します。
近年、生活者がSNSでつぶやく頻度が落ちていると感じます。よほど感動的な体験か、自分が好きなものでないと、なかなか口コミやUGC(ユーザー生成コンテンツ)は生まれません。「ブランド没入型体験プロモーション」で、熱量の高いUGCを生み出すためには、どのような仕掛けが必要だとお考えですか。
久野:
スペースマーケット側の視点で言うと、まず「良い体験になっていること」が大前提です。「ここに来てすごく楽しかった」「これをやってみて本当に良かった」という状態を作ることがスタート地点だと思います。
その上で、SNSに投稿する「理由」を作ってあげることが重要だと考えています。
この間、プライベートで訪問した大阪・関西万博でも、入り口に大きなミャクミャクのオブジェがあり、そこで多くの人が写真を撮っていました。そのオブジェは、「自分が万博に来たことを表明できる場所」として機能しているわけですよね。
三島:
ユニバーサル・スタジオ・ジャパンに行ったときも、アトラクションを楽しんでいる最中はあまり写真を撮らないけれど、帰りに地球儀の前で記念撮影するという感覚に近いですね。
まずは「良い体験」を作り、それを広げていきたい
三島:
余談なのですが、以前、弊社のクライアントから「マーケティングすぎる」と言われたことがあって、結構衝撃を受けたことがあります。その背景には、「マーケティングは重要だけれど、私たちはそういうことをやりたいわけではない」という意思表示の気持ちがあったのだと思います。
久野:
秀逸な言葉ですね。
三島:
大きな成果を生むために、色々なテクニックやひねりを入れすぎた結果、温かみがなくなってしまうというケースは多々あります。
スペースマーケットさんとの取り組みにおいても、ポップアップや旗艦店では提供できない、深い体験を提供することが鍵になると思います。そういった意味で、「ブランド没入型体験プロモーション」は「N=1の顧客に対して良い体験を提供する」という、シンプルな価値観に回帰できるサービスになると感じました。
スペースマーケットさんは今後、このプロモーションをどのように展開していきたいですか。
久野:
スペースマーケットとしても、まず「この場所で面白い体験ができた」という事実を企業の方々と積み上げていきたいです。とはいえ、このサービスはまだ世の中に存在しないものであり、方法論が確立されていません。企業様やテテマーチさんと一緒に、その最適解を模索できればと考えています。
三島:
その過程で、ブランドのファンがスペースマーケットで特別な体験をして、それが広まることでスペースマーケットの空間にも興味を持ってもらう。そんな流れが生まれると理想的ですね。
久野:
それは副次的な効果として期待したいですね。単に部屋を借りるプラットフォームではなく、「良い体験ができる場所」という認知が広がれば、企業も参入しやすくなるのではないでしょうか。
そのための最初のステップとして、サービスのコアである「良い体験」を作ることに注力したいです。あらゆる手を尽くして最高の体験を追求する。それが一度形になれば、「この部分は削っても体験価値は損なわれない」という輪郭が見えてくるはずです。
そこで研ぎ澄まされたエッセンスを、他のさまざまなスペースに展開していくことで、素晴らしい体験を世の中に広げていきたいです。

今回の取材では、スペースマーケットの利用者が自発的に生み出す「没入体験」を起点に、企業がファンと熱量の高い関係性を築くための新たなプロモーションの可能性について、示唆に富むお話を伺うことができました。
改めまして、久野さん、この度は取材にご協力いただき、本当にありがとうございました。


本サービスは、リアルな空間でのブランド体験とSNSでの拡散を連動させ、ファンとのエンゲージメントを飛躍的に高める、新たなマーケティングアプローチです。テテマーチが持つSNS分析・運用ノウハウと、スペースマーケットが展開する日本最大級のスペースシェアの力を組み合わせ、データドリブンで最適な“語りたくなる体験”を企画・提供します。
詳細資料は下記からご覧いただけますので、お気軽にダウンロードください。