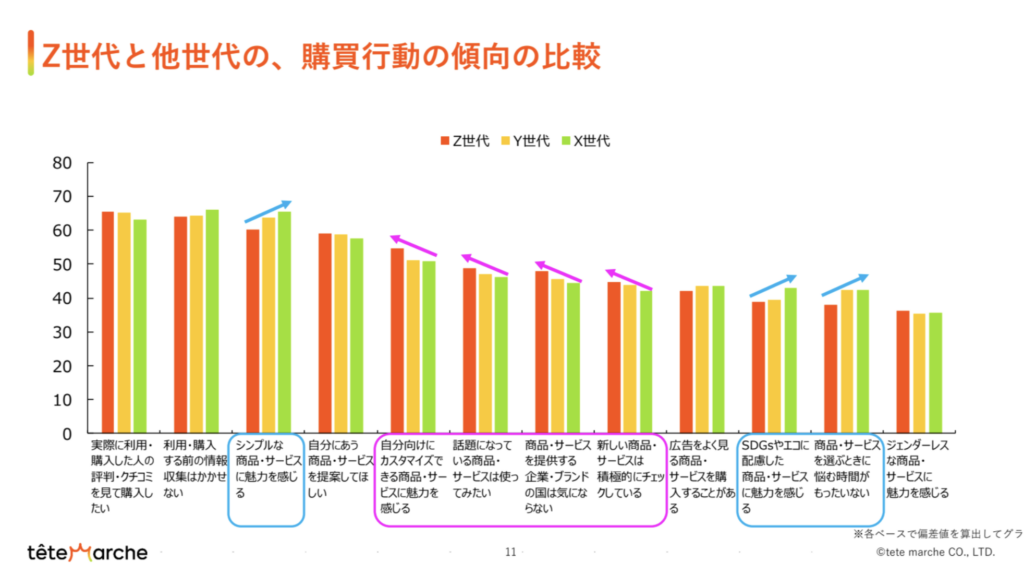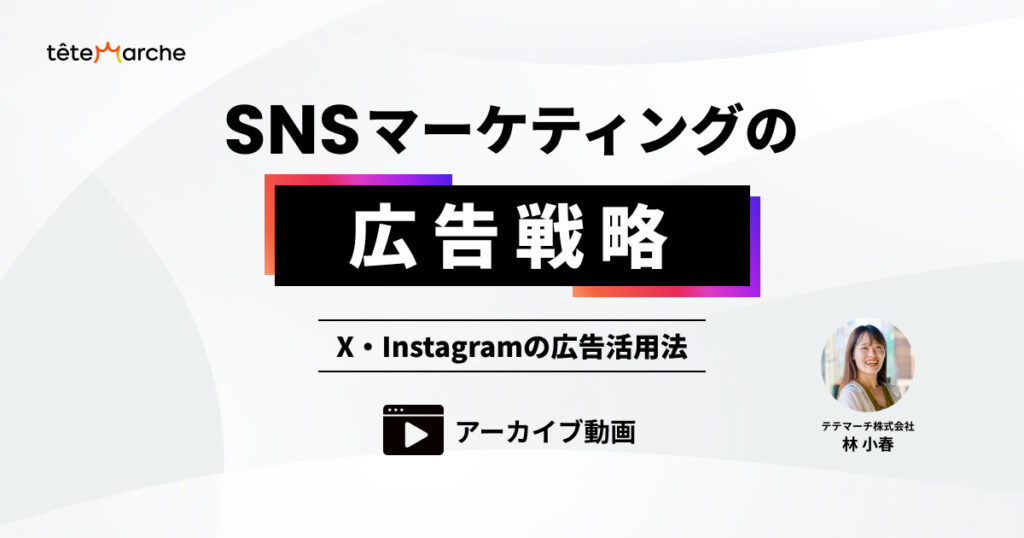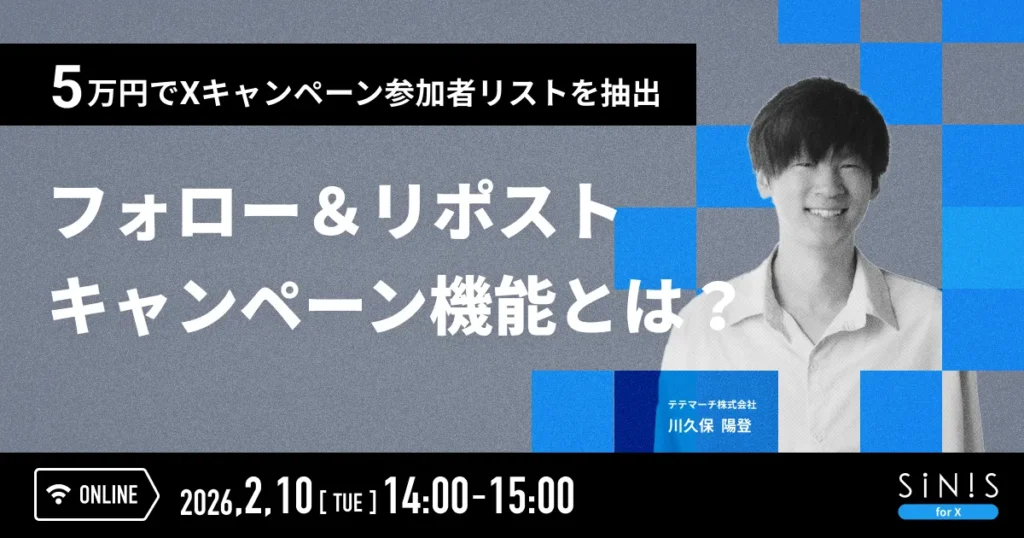韓流ブームからアジアミックスへ。原田曜平が語る、Z世代の最新トレンドと企業の向き合い方
Date : 2025/04/15
若者研究・メディア研究の第一人者で、「さとり世代」「ヤンキー経済」「Z世代」など、さまざまな言葉を生み出してきた原田曜平さん。現在は、芝浦工業大学デザイン工学部UXコースの教授でありながら、韓国や中国、アメリカなど世界各国をめぐり、現地での調査をしつつ若者の消費行動を研究しています。
今回は、そんな原田さんに「Z世代の最新トレンド」についてお伺いしました。SNSの利用実態、韓流ブームの現在地、今後のトレンド動向など⋯。Z世代の今を深堀りしつつ、上の世代や企業がZ世代にどう向き合うべきかを議論しました。
目次
BeReal.の人気が続きそうな理由とは?
三島悠太(テテマーチ執行役員/ビジネスプロデューサー):
この1年間で、Z世代の消費行動やメディア利用に変化はありましたか?
原田曜平さん:
一番の変化といえば、「BeReal.(ビーリアル)」がものすごく普及したことです。BeReal.は昨年もっとも伸びたSNSで、高校生の3割、女子大生の3割が使っています。Z世代全体でいうと、2割程度まで浸透していますね。
三島:
他のSNSのようなフィルターや編集機能がなく、撮影した写真を加工できないことから、「ありのままの自分」を共有できるというコンセプトですよね。
これまでいくつものSNSが、登場しては淘汰されてを繰り返してきました。BeReal.はこの先、まだまだ伸びていくと思いますか?
原田:
イノベーター理論に照らし合わせると、16%がキャズムだとされているので、Z世代のキャズムは超えたという感覚があります。とはいえ、BeReal.が今後も続くかどうかの見方は分かれていますね。
「続きそう」だと言える理由は、とても楽であること。
BeReal.は、アプリからの通知が来たら2分以内に投稿しないといけません(2分を過ぎても投稿自体は可能)。急いで投稿しなくてはならないので大変ですが、「ただ撮ってシェアするだけでいい」と言い換えることもできます。
若い子たちは“捨てリアル”と表現していて、例えば「今は電車の中だから自分のネイルだけ撮影して投稿する」だけでいいという手軽さがBeReal.の大きな特徴です。

三島:
InstagramやTikTokのような加工の煩わしさがなく、写真をサクッと撮るだけでいいわけですね。
原田:
BeReal.も、限られた2分間のなかで「部屋で撮るならここが一番キレイ」「この角度から撮ろう」「簡単にファンデーションだけ塗っておこうかな」と、さまざまな工夫が必要です。それでも、InstagramやTikTokに比べればよっぽどハードルが低い。慣れると誰でも簡単に使えるので、私はBeReal.を「最も楽なSNS」と表現しています。
一方で、続かないと考える理由もいくつかあります。
まずは社会的なモラルの問題です。
「通知が来たら2分以内に写真を投稿しないといけない」というBeReal.のルールが、すでに一部の企業で問題視されています。というのも、会議など仕事中にも関わらず、急にスマホで写真を撮り始める社員が出てきているからです。
アプリの特徴であるリアルタイム性と、TPO(時間・場所・場面)をわきまえた使い方との両立が今後の課題と言えるでしょう。こうした課題に向き合いつつ、社会人にどう根付かせていくかがBeReal.普及の分かれ道だと思います。
もうひとつの理由は、グローバルな視点で見ると、フランス、アメリカ、日本と局所的にしか普及していないということです。私が韓国や上海、台湾などに現地調査へ行ったとき、ほとんどの人がBeReal.を知りませんでした。
三島:
アジア全体には広まっていないのですね。日本のトレンドは韓国から火がつくケースが多いので、今の状況は気になりますね。
原田:
NewJeansなどのK-POPスターがBeReal.を始めたら一気に広がる可能性はありますが、今のところその兆候はまだないですね。
これからの流行は「韓流ブーム」から「アジアミックス」へ
原田:
ただ、今までの「韓国から日本へ」というトレンドの流れは今後変化するかもしれません。おそらく近いうちに、韓流ブームは終わりを迎えると考えています。
三島:
どういうことですか?
原田:
韓国や日本の若者に人気の映像作品を聞くと、これまでは『梨泰院クラス』『イカゲーム』『サイコだけど大丈夫』など、韓流ドラマがメインでした。しかし、いくつかのプチヒットも含めて、現在は『涙の女王』以降、若者から韓流ドラマのタイトル名を聞きません。
逆にここ半年は、日本のアニメやドラマが真っ先に挙がるという現象が続いています。K-POPもNewJeansを最後に、あまり火がついていない気がします。
三島:
各グループのコンセプトが似通っていて、飽きられているということでしょうか。
原田:
それもあると思います。韓国には聖水(ソンス)という人気エリアがあり、日本でいう表参道のような場所で、日本人女性にも人気です。ここに足を運んでも、コスメの新作などをあまり目にしなくなりました。
こうした様子から、ここ10〜15年で爆発的に人気を伸ばした韓流ブームが、下火になっているのを感じます。
逆に注目されているのが、他のアジア諸国のトレンドです。
例えば中国を見ると、TikTokやSHEINといったアプリが人気で、中国コスメも日本にどんどん進出しています。上海にはかわいい雑貨屋さんが多く、ぬい活*の聖地のような場所になっているのです。
先日タイに行ったのですが、バンコクにも「バターベア」という可愛いぬいぐるみがいたり、BLドラマが流行っています。そんなタイの若者に話を聞くと、今はベトナム風ファッションがトレンドだと言うのです。
今後、「どこの国が発祥なのかわからないけれど、アジア発のものが流行る」といったアジアミックスが、ますます進むと考えています。
三島:
非常に興味深い傾向ですね。日本を含むアジア諸国の若者の態度変容に影響を与えている要素は何なのでしょうか?
原田:
やはりSNSの影響が大きいです。それを象徴する面白い話があります。
以前、上海での現地調査をするにあたって、何人かの日本人大学生に上海のトレンドスポットの調査と、そのリスト化をお願いしました。同時に、現地のマーケティング会社にも同様の調査とリスト化を依頼しました。
すると、学生たちの出してきたリストが、現地の会社と同等、あるいはそれ以上の出来栄えだったのです。
学生たちは中国のSNS「RED(小紅書)」を活用して、行ったことのない国のトレンドを、現地に住んでいるリサーチのプロより正確に感知していました。この事実を目の当たりにして、恐ろしい時代になったと実感しました。
*ぬい活:お気に入りのぬいぐるみと一緒に出かけたり写真を撮ったりすること。
アジア諸国の若者はよりリアルな日本を求めている
三島:
アジア諸国から日本へとトレンドが流入するのとは別に、アジア各国で人気の高い日本のコンテンツはあるのでしょうか?
原田:
5〜10年前までは、日本車がブームでした。今、世界中の若者に聞いて真っ先に浮かび上がるのは日本食、それからアニメではないでしょうか。あとは『ちいかわ』のようなキャラクターも人気が高いです。
ただ、日本によく訪れる韓国人に「なぜ日本に来るの?」と聞くと、意外にも曖昧な回答しか返ってきません。
昨年、韓国で調査したときにも印象的だったのが、多くの若者が日本観光の理由を「ノスタルジー」と答えるのです。
三島:
ノスタルジー?日本が?
原田:
ある意味で屈辱的な言葉ですよね。日本に明確なトレンドがあるわけではないと言われているのと同じですから。
日本よりはるかに厳しい競争社会で、貧富の差が広がっている韓国の人々にとって、日本はとても平和な場所に見えるようです。街がキレイで人は穏やかで、外食に行っても接客が丁寧。昔の韓国にもあった温かさが日本にはある。それを若者は「ノスタルジー」と表現したのだと思います。
三島:
なるほど⋯。この話を踏まえつつ、SNSでコンテンツをシェアしてくれる人の特性を見極めてプロモーションしないと、日本発のコンテンツやトレンドは広まらないかもしれませんね。

原田:
以前、タイのインフルエンサーであるびーむ先生(Beam Sensei)にインタビューしたことがあるのですが、彼女は日本の情報発信者として非常に有名で、自治体のPR活動をしたりもしています。びーむ先生に「タイの若者は日本に何を求めているのか」と聞いたところ、彼女はこう答えました。
「タイには日本食のレストランがたくさんあり、日本に行った経験がある人も増えています。よりリアルな日本、あるいはちょっと過激な日本じゃないと、若い世代には受けなくなっています」
例えば、田舎に行って自然や温泉を楽しんだり、森林の中でバギーを乗り回したりなど、リアルな日本を楽しむ方向に若者の志向がシフトしていると、びーむ先生は言っていました。
現在、自治体の発信活動の大半は、インフルエンサーとコラボして主要な観光スポットを紹介するというものばかりで、ほとんど一過性で終わってしまいます。こうした単発のインフルエンサー企画ではなく、何気ない日常の風景など、日本の「リアルな魅力」をもっと発信していく必要があると思います。
ドメスティックな思考をやめてグローバルな視点でZ世代を捉える
三島:
企業も自治体も、発想を転換してマーケティング戦略を練り直さないといけませんね。
原田:
私がマーケティングに関する相談を受けて痛感するのは、日本企業のドメスティックな思考です。
ある企業から若者向けの施策を一緒に考えてほしいと相談されました。しかし、最終的にこのプロジェクトは「Z世代という小さいパイ(市場)に予算を割くことはできない」という理由で中止されたのです。
この発想自体が古いのではないかと思います。実際、韓国は日本よりもはるかに若者市場が小さいのに、国をあげてビジネスを盛り上げて、海外の若者をターゲットに韓流ドラマやK-POPを生み出してきました。

三島:
その結果、BTSやBLACKPINKなどがグローバルでも大ヒットしたわけですもんね。
たしかに日本の場合、国内だけに目を向け、少子化で市場が縮小しているからといって、購買力のある中高年やファミリー層にターゲットを絞るという意思決定も目立ちます。
原田:
でも言い換えると、これはチャンスでもあります。なぜなら、SNSによって世界中のZ世代が得る情報も価値観も似通ってきているからです。
アメリカと日本の若者の間で、TikTokやNetflixで流行っているものは大抵同じと言えます。日本では今、グミ市場が急激に伸びていますが、韓国の若者が日本に来て欲しがるのもまたグミなのです。
少子高齢化が進んでいるとはいえ、日本の若年層でも1学年あたり100万人程度はいますし、東南アジア約6億人の平均年齢は20代。中国を加えると、さらに数は増えます。
例えば、日本では若者のお酒離れが進んでいますが、韓国の若者にインタビューすると、「日本の生ビールはすごくおいしい!韓国とは比べ物にならない」と絶賛してくれるのです。それならば、韓国で美味しい生ビールを提供できるお店を作れば、逆輸入の形で日本でも生ビールブームが起こる可能性があります。
三島:
グローバルの視点に立つことで、新しいトレンドを生み出せる可能性が出てくるわけですね。
原田:
日本企業はまだまだ国や地域を分割して考えがちです。Z世代をひとつの塊として見れていないからこそ、チャンスを逃してしまっているのではないかと思います。
日本の若者に限定せず、「Z世代市場」というひとつの市場がグローバル規模で形成されていることに、日本の企業や自治体には早く気づいてほしいです。
Z世代とのコミュニケーションは「近づいて寸止め」がポイント
三島:
企業に限らず、上の世代もまたZ世代とのコミュニケーションに失敗しがちですよね。Z世代に嫌われたり反感を買ったりするコミュニケーションには、どのような傾向がありますか?
原田:
中高年の多くは、LINEなどのコミュニケーションツールでのやり取りやパワハラ発言の録音を人事に持ち込まれたりすることを恐れて、「距離を取る」という選択を取っています。
実はこれが一番ダメなことだと感じています。普段から距離を取ってコミュニケーションを避けているせいで、Z世代の本質がわからないから、ふとしたタイミングで間違った言動に走っちゃうことが、最悪なパターンなんですよね。
面倒に感じられても、普段から「近づいて止まる」習慣を持つことがとても大事です。
三島:
たしかに、日頃から近い距離で接し、信頼関係や心理的安全性を保っておくことは大切ですよね。
原田:
私も、「近づいて止まる」を自分に言い聞かせながら学生とコミュニケーションしています。君子危うきに近寄らずではなく、言動には十分注意しつつ相手に近づくことが、我々の世代には必要なのかなと。
それに、距離を取ってしまうことで、Z世代が上の世代について学ぶ機会を失ってしまいます。
以前、サントリーさんに「新入社員向けに講演してほしい」と依頼されました。若者にZ世代の話をするのは違和感があったのですが、サントリーさんの依頼内容は全く逆で、「新入社員に向けて上の世代の話をしてほしい」というものでした。
団塊世代や団塊ジュニア世代が、どのような有名人やアーティストを見て育ったのか。それを説明することで、自分の上司の価値観や感性を理解しやすくなります。上の世代の価値観をただ押し付けるのではなく、相互理解を深めていこうと考えたサントリーさんの姿勢は、さすがだなと思いました。
三島:
若い世代も、上の世代のことを知りたくないわけじゃないですもんね。

原田:
以前、NewJeansのメンバー・ハニさんが松田聖子さんの『青い珊瑚礁』をカバーしました。その影響からか、韓国の若者も普通に『青い珊瑚礁』を歌います。このことを中高年世代に話すと、「カラオケで聖子ちゃんを歌ってもいいの!?」と驚くんですよね。
相手を知ろうとせずに離れるのではなく、知るために近づくこと。自分たちの価値観を押し付けるのではなく、ただ伝えていくこと。両方の姿勢が、上の世代にとって大切だと思います。
徹底的にリサーチするか、ありのままに正直でいるか
三島:
原田さんのお話を聞いて、やはりZ世代からの支持を得ることは、これからの企業にとって絶対的に必要であると改めて実感しました。彼らに支持されるブランドを作るために、どのような広告的アプローチやSNSでのコミュニケーションが必要だと思いますか?
原田:
そのテーマのカギを握るのは、日清食品さんとサントリーさんの2社だと思います。
例えば日清食品さんは、SNSでのニッチなネタをテレビ広告でよく使用しています。Z世代はあまりテレビを見ていませんが、今もテレビメディアは権威性が高いという感覚はあります。
そのため、「自分たちしか知らないネタがテレビで扱われている!」と驚き、「この会社は自分たちをよく見てくれている」と感じます。
サントリーさんも、ネルソンズ・和田まんじゅうさんが「後輩を飲みに誘えない先輩」を演じたCMで話題になりました。CMで繰り広げられる先輩と後輩のやり取りが、若者にとってあるあるな光景としてとてもウケたのです。
今後のCMやマスメディアは、若者を起点に展開することが重要になると思います。
SNSの人口はZ世代が中心で、彼らは両親と良好な関係を築いていることが多いです。そのため、若者を起点とすることで、それが自然と上の世代まで拡散される可能性を秘めています。
三島:
Z世代をファーストターゲットと捉えることで、逆に他の世代にも広がる可能性があると。そしてSNSを通じて、グローバルに広がる可能性もあるということですね。
原田:
一番やってはいけないパターンは、本質を理解せずに表面上だけZ世代の文化を取り入れようとすることです。これは毎年行う調査でも、ハッキリと広告効果が低いことがわかっています。
例えば、「〇〇しか勝たん」という言葉がありますよね。自分の推しに対してよく使う言葉ですが、それを異なる文脈で使用すると、Z世代には違和感になってしまうのです。
三島:
トレンドを押さえ間違ったり、インサイトを履き違えたりすることが、一番の失敗要因になるわけですね。Z世代のインサイトをどれだけ把握できているかが、企業のブランディングでは重要だということがわかります。
原田:
逆に言うと、変にカッコつけたり迎合したりせずにありのままを発信するほうが、Z世代には受け入れやすいんですよね。TikTokでは「天国界隈」といって、おじいちゃんが不器用に踊っている動画が人気だったりします。
Z世代からすれば、微差がもっとも目立つのです。逆の道を行くのであれば、「正直たれ」という姿勢が、Z世代からの支持を得られるポイントだと思います。
三島:
やりきるか、着飾らず正直でいるか、どちらかを見極めることが企業のブランディングを左右するのですね。

編集後記
常にトレンドの兆しを捉え、未来を見据える原田さんの視点には、取材中何度も唸らされるばかりでした。
さて、本編ではスペースの都合上、残念ながらカットせざるを得なかったのですが、取材の合間には原田さんの意外な(?)一面が垣間見える、こんなやりとりもありました。
編集部: Z世代より上で、BeReal.を一番使いこなしているのは原田さんじゃないですか?
原田: これがそうでもないんですよ。私も毎日頑張って投稿しているんですが、『孤独のグルメ』のようにご飯ネタしかなくて。自分のメモリー(過去の投稿)を見返すと切なくなります(笑)。 若い世代がご飯ネタだけで面白がってくれているのかわからないので、もっと研究室の学生と一緒にいろいろ投稿したいんですけどね。
最新のSNSにも積極的に触れられている原田さんですが、その投稿内容が『孤独のグルメ』状態とは、なんとも親近感が湧くエピソードですね。ご自身のメモリーを「切ない」と笑いながら語る姿や、若い世代とのコミュニケーションを模索されている様子に、原田さんの誠実でチャーミングなお人柄を改めて感じました。
改めまして、原田さん、この度は貴重なお話を本当にありがとうございました。
テテマーチでは、Z世代向けのプロモーションプランニングや、Z世代を対象にした調査などを行なっています。調査レポート資料は下記からご覧いただけますので、お気軽にダウンロードください。